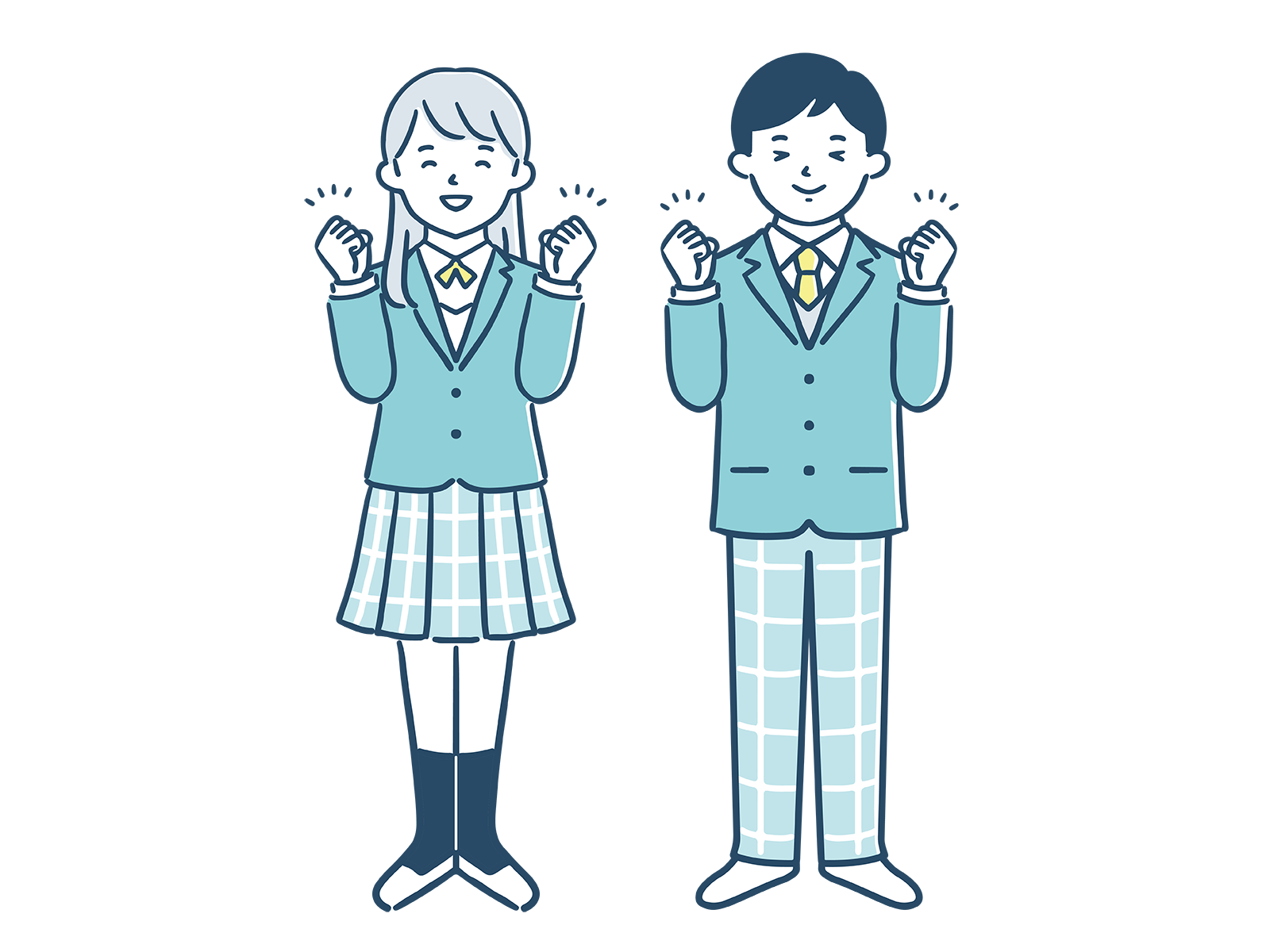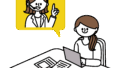「子どもの勉強、いつまで並走すべきですか?」
よく聞かれる悩みですが、私はこう思っています。
答えは「本当に個人差がある」ということ。
お子様が不安なうちは、並走してあげるべきでだと思います。
でも、ひとつ言えるのは
小学生のうちは、できるだけ並走してあげた方がいいです。
といっても、毎日隣に座って一緒に勉強するという意味ではありません。
「問題のコピーを取ってあげる」
「ワークのページを一緒に確認する」
「やり方のコツを教えてあげる」
そんなちょっとした環境づくりや伴走が、並走だと思っています。
中には、教科書の内容をまとめてノートにしてあげるようなお母さんもいます。
もちろん、それでうまくいくなら◎ですが…
高校の勉強は内容が格段に難しくなり、親が並走するのは現実的にとても厳しい。
高校生になると、「自分と同じくらいの成績の子」が集まる世界になります。
うちの娘が公立中学から高校に入ってまず感じたのは、定期テストのレベルが模試並みに難しいということ。
娘の学校では、テストの内容も9割が応用問題、残り1割が基礎…そんな印象でした。
そしてもうひとつ大切なのが、
「提出物などの内申点の重み」。
高校ではひとつひとつが本当に重要です。
だからこそ、中学生のうちに全部親が管理してしまうのではなく、「自分で管理する力」を少しずつ育てておくのが大事。
高校生活って、通学や部活、朝も早くなって…とにかくバタバタします。
その中で勉強をまわしていくには、やっぱり自分のペースでやり切る力が必要なんですよね。
親に手を引いてもらうことに慣れてしまっている子は、自己管理がうまくできず、つまずくケースもあります。
だからこそ、並走にもフェードアウトの準備期間が必要だなって思います。
中学生の間に少しずつ距離をとりながら、
自分で時間を管理する力をつけていけたらベストです。

勉強の並走は、ずっと一緒ではなく、いつか手を離すためのもの。
親として少しずつ見守りの形にシフトチェンジが必要だなぁと思います。