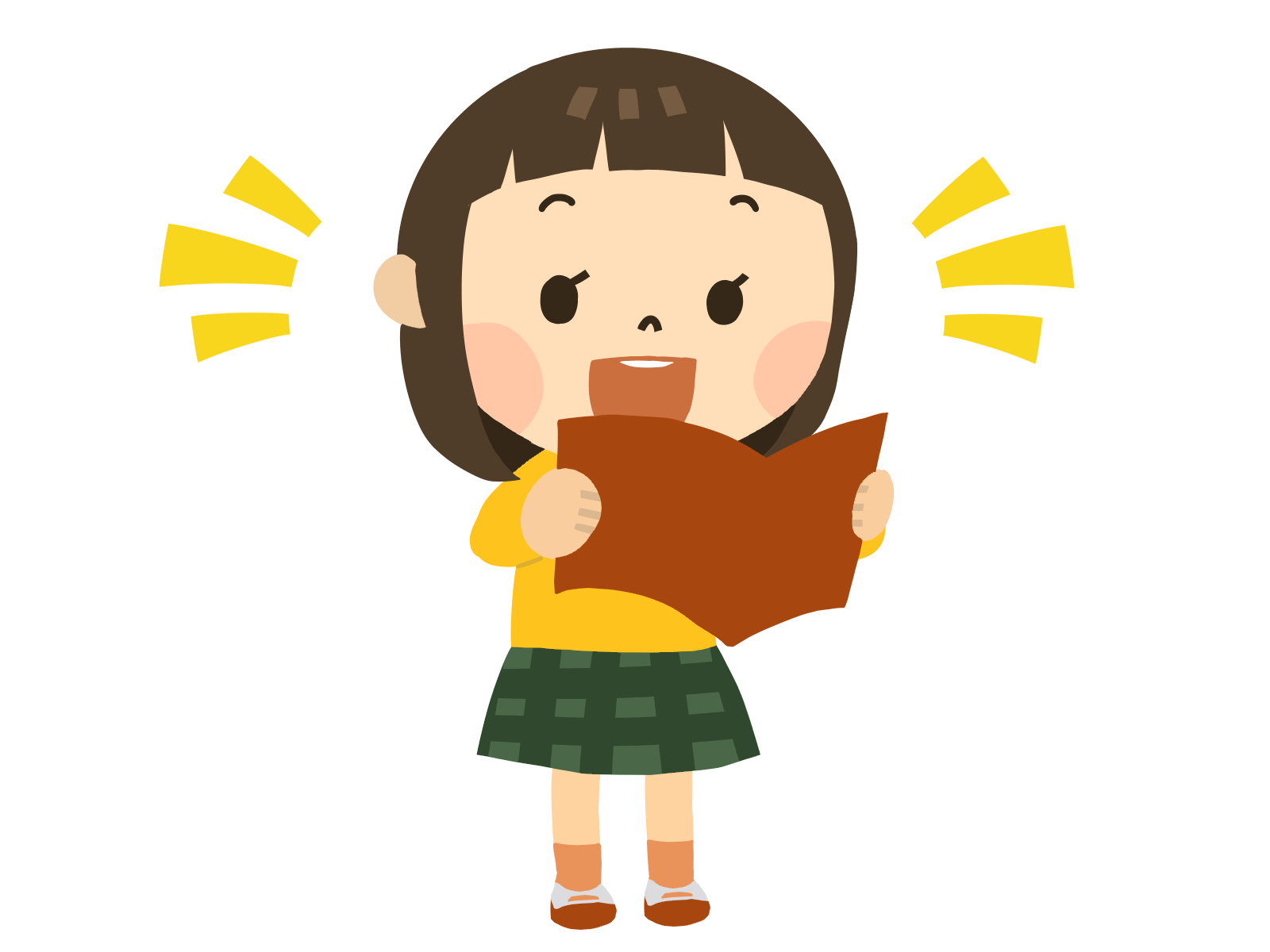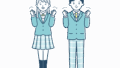小学校では「音読をしなさい」とよく言われました。わたしも言われて育ちました。

低学年のうちは、声に出して読むことで文章のリズムや言葉の響きを体感して読むことへの抵抗感を減らすという意味で、とても大切な学習です。
ただ我が家の長女、次女もあまり読まなかったです。
小1、小2の頃は読んでいました。
学年があがるにつれて読まなあかんで、宿題やで、といってもめんどくさいという。
そのやりとりが続いて(結構このやりとりがめんどくさい)、
そもそもなんで読まなあかんのやろうとふと私が思って色々調べました。
わが家では途中から「黙読力」を重視するようにしました。
音読は音声化することが目的になりがちで、「読んだ気になる」ことがあります。
一方、黙読では、内容を理解する・つながりを考える・要点をつかむということが必要になります。わからなかったら文を戻って読みますよね。
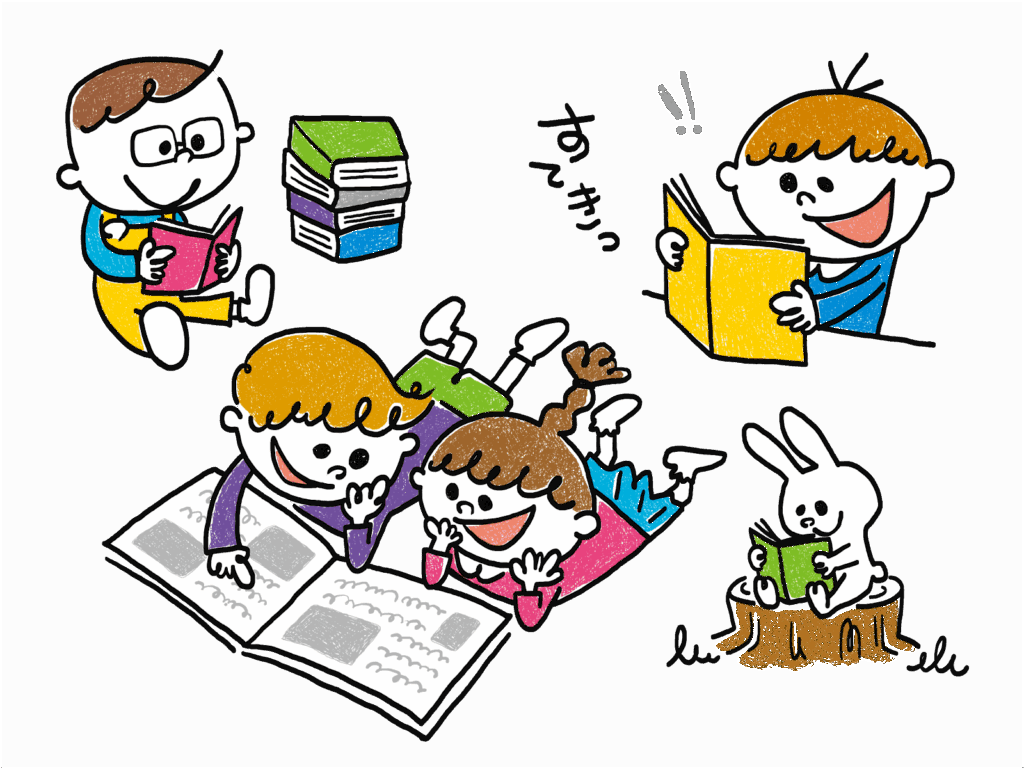
その結果、読解力・集中力・速読力などが自然と養われていくのではないかと考えました。
また一方で英語に関しては「音読」が非常に効果的だと感じています。
中学生の英語の宿題で音読があっても良いくらいと思うほど効果あると思っています。
英文の場合、音声化することで
・発音やイントネーションの習得
・英文構造の定着
・リズム感と語順感覚の養成
・リスニング力への好影響
など、言語習得の基盤となる感覚を育てることができるからです。
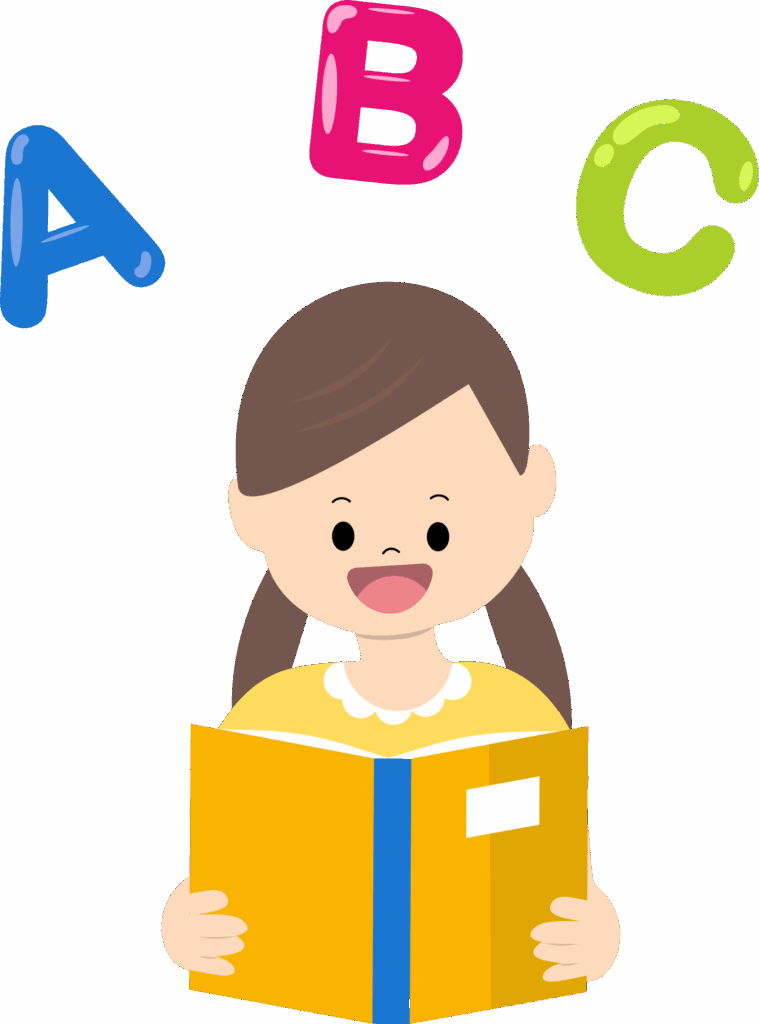
音読することで、英語の語順やリズムを身体で覚えることができ、自然な読み方や話し方につながります。
特に英語は、日本語と文の構造が異なるため、
「日本語は黙読で深く考える力を育てる」
「英語は音読で言語感覚を身につける」
というように、それぞれの言語に合わせた学習スタイルを意識することが、効果的な学びにつながると考えています。
ここまで読んでくださってありがとうございました。